歩き人たかちです(@takachi_aiina)
山歩きで身体の負担を減らし、バランス補助として有効な"トレッキングポール"。
手に持って歩くのが煩わしくて使っていませんでしたが、相棒にモンベル「U.L. フォールディングポール 100」を選びました。
「U.L. フォールディングポール」に"100cm"が登場したとき、ポールを使うならこれ、と決めていました。低身長の自分にはぴったりサイズ。
使用時も携行時も気にならない、わずか149gのコンパクトな「U.L. フォールディングポール」ですが、細すぎない?折れない?調節できないってどうなの?など、さまざまな疑問があると思います。
ニュージーランド3,000kmのロングトレイルで毎日使用した体験をもとに、実際の使用感をご紹介します。
トレッキングポールを購入した理由
不要だと感じていたトレッキングポールを購入した理由は、大きく2つ。
◾︎ 海外ロングトレイルで必要
膝への負担を減らしたい
一般的に「体重が1kg増えると膝への負担は3〜5kg増える」といわれています。重い荷物を背負い、登り下りを繰り返す登山では膝への負担が大きい。
膝痛はないものの、南アルプス南部を縦走したとき、易老岳への急登で「膝がかわいそうだ」と思うように。
*2024年夏、トムラウシ縦走で膝痛を発症。ニュージーランドのロングトレイルでの酷使が大きな要因でした・・・
20代は体力任せでガンガン山を歩いていましたが、30代で軟骨がかなりすり減っている知人もいて(軟骨は消耗品)、人生長く歩くために身体を大事にしようと思いました。
海外ロングトレイルで必要
2023年12月〜2024年4月に歩いた、ニュージーランド3,000kmのロングトレイル「テ・アラロア / Te Araroa」。

ニュージーランドは"渡渉"がとにかく多く(グレート・ウォークなど有名なトレッキングコース以外は大体ある)、ウエスト前後の渡渉もあるテ・アラロアではもはや必須装備。
また、太ももまで埋まるような泥沼もあるし、アップダウンも激しい。バランス補助はもちろん、3,000kmという未知の距離を歩くためにトレッキングポールを購入しました。
トレッキングポールの選び方
トレッキングポールは大きな区分から絞っていき、細かい仕様を比べるのがベストだと思います。
◾︎ 伸縮式 or 折りたたみ式
◾︎ アルミ or カーボン
◾︎ ツイストロック or レバーロック
◾︎ 長さ・重量のバランス
◾︎ その他細かい仕様
「I字型」or「T字型」
トレッキングポールの形状は「I字型」「T字型」の2種類。これは、持ち手部分のグリップの形状です。
| 特徴 | |
| I字型 | ◾︎ バランス補助 ◾︎ 2本使いで推進力を得られる ◾︎ 重い荷物を背負う際の負担軽減 ◾︎ 起伏が多いトレイル向け |
| T字型 | ◾︎ バランス補助(主に1本使い) ◾︎ 普段の歩行に近い感覚で使用できる ◾︎ 握る力が少なくて済む ◾︎ 起伏が少ない整備されたトレイル向け |
\I字型 /
画像出典:モンベル
登山で主流なのは「I字型」。バランス補助に加え、2本使いをして"推進力"を得られます。
1本使いも可能ですが、よりよいバランス力と推進力を求めるなら2本がおすすめ。1本の場合、筋力バランスが悪くならないよう、左右で持ち替えながら使うとよいです。
正しい使い方は、グリップは軽く握るだけで(手を添える程度)ストラップに荷重をかけます。I字型を正しく使うには練習と慣れが必要なので、山で実践できる講習会などへの参加もおすすめ。
\ T字型 /
画像出典:モンベル
「T字型」のトレッキングポールは上から手を乗せる(被せる)、杖と同じような使い方。面積が広く、「I字型」に比べて握る力は少なくて済みます。
1本使いが主流で(2本使いする人もいる)、推進力ではなく"歩行の補助"を目的としたもの。
起伏が少ない整備された登山道に適しており、低山や木道ハイキングなど、普段の歩行に近い場面で使いやすいです。
\ 2つを合わせた「2way」モデルも!/
画像出典:モンベル
モンベルには、「I字型」と「T字型」を合わせた"2wayモデル"もあります。
登りでは持ちやすい「I字型」、下りでは体重をかけやすい「T字型」というように、状況に応じて使い分けができます。
重量が多少重いことがデメリットですが、どちらも使いたい人にはおすすめ。
「伸縮式」or「折りたたみ式
トレッキングポールは、伸ばして使う「伸縮式」と、組み立てる「折りたたみ式」があります。
| 特徴 | |
| 伸縮式 | ◾︎ 長さの調節幅が広い ◾︎ 耐久性が高い ◾︎ 収納時のサイズは長め ◾︎ 分解可能で中のメンテナンスは容易 |
| 折りたたみ式 | ◾︎ 軽量コンパクト(ザックの中に収納できるモデル多数) ◾︎ 長さ調節不可 or 少しだけ可能 ◾︎ 修理が複雑になることもある |
「伸縮式」は上・中・下段の太さが異なり、中段と下段をそれぞれ伸ばして使うタイプ。「I字型・伸縮式」は、種類が豊富なスタンダードモデルです。
長さ調節の幅が広いので、平地から急斜面まであらゆる場面に適していることがメリット。また、耐久性も高いので、安定した補助を求める人におすすめ。
「折りたたみ式」よりも収納時のサイズは大きいですが、上・中・下段すべて分解できるためメンテナンスは容易。折れた場合は、折れたシャフトを交換すればいいので、修理も早く済みます。
\ 折りたたみ式 /

「折りたたみ式」は基本的に上・中・下段の太さが同じで、紐などで連結されています。
比較的軽量コンパクトで、ザックの中に収納しやすいモデルが多いことはメリット。
デメリットは、長さ調節不可のモデルが多いこと。多少調節できるものもありますが、「伸縮式」ほどできないものがほとんど。

上段でサイズ調整ができる「折りたたみ式」。20cmの調節幅があります。
「アルミ」or「カーボン」
| 特徴 | |
| アルミ | ◾︎ カーボンより重い ◾︎ 素材の「粘り」により折れにくい ◾︎ 比較的安価 |
| カーボン | ◾︎ 軽い ◾︎ アルミに比べて折れやすい ◾︎ 価格が高い |
「アルミ」は素材特有の粘り(しなり)があり、衝撃が加わった際は折れる前に曲がります。強い衝撃でバキッと折れることもありますが、カーボンに比べて折れにくいことがメリット。
積極的に体重をかけて使うものではありませんが、下りや万が一体重をかけてしまったときに安心感があるのはアミル。
デメリットは、カーボンよりも重いこと。重量によっては、長時間の使用や携行が負担になることも。
しかし、現在はアルミの軽量モデルも多いので、大きなデメリットにはならないかもしれません。店頭で持ち比べることをおすすめします。
* * *
「カーボン」は"軽い"ことがメリット。長時間の使用や、念のため持って行くという携行で負担を減らせます。
デメリットは、"一点集中の衝撃(力)に弱い"こと。素材自体の強度は高いですがアルミほどの粘りはなく、いきなりバキッと折れることがほとんど。
多少曲がっただけなら下山まで使えますが、折れたらその場で補修が必要。トレッキングポールの修理は、カーボンが圧倒的に多いです。
上段はアルミで中・下段はカーボンなど、耐久性と軽さのバランスが考えられたハイブリッドモデルもあります。
「ツイストロック」or「レバーロック」
長さ調節の形式に「ツイストロック(スクリューロック)」と「レバーロック(カムロック)」があります。
| 特徴 | |
| ツイストロック | ◾︎ レバーロックよりも構造がシンプル ◾︎ パーツが少ない分多少軽量の場合も ◾︎ 雪山では回す部分が氷結することもある |
| レバーロック | ◾︎ ワンタッチで素早く調節可能 ◾︎ パーツが少し複雑 ◾︎ 雪山でも使いやすい |
\ ツイストロック(スクリューロック)/
画像出典:モンベル
「ツイストロック」は、繋ぎ目のパーツを回して長さを調節するシンプルな構造。
中にはストッパーのパーツがあり、すり減ったり割れたりした場合は交換可能。
雪山では"氷結して回せない"ことがあるため、オールシーズン使う場合はその点に要注意。
また、錆やストッパーの消耗・ひび割れ、パーツとシャフトの間に砂などが入り込んで固着すると、「回しても閉まらない」「回らない(パーツが動かない)」などの不具合が生じます。
使用中はシャフト内に水蒸気が溜まり、塵埃も付着するので、使用後は上・中・下段すべて分解して拭き取りと乾燥を。
メンテナンスでバラしていて、いざ使おうとしたら中段がない!なんてことも起こり得るのでご注意を。
\ レバーロック(カムロック)/
画像出典:モンベル
「レバーロック」はレバーの開閉で調節するワンタッチ構造。「ツイストロック」よりも素早く調節できます。
パーツが少し複雑になるので破損や故障のリスクは「ツイストロック」よりも高く、登山中にネジの緩みが生じると「ロックがカチッと留まらない」「緩くてシャフトが引っ込んでしまう」ということも。
雪山では「ツイストロック」のような氷結は少なく、厚手の手袋でも扱いやすいので、オールシーズンの使用には向いています。
「長さ」と「重量」のバランス
平地で肘が90度に曲がるくらい
長さの目安でよく言われますが、個人的には"90度より少し下"がちょうどいい。平地で推進力を得る場合、ちょっと腕が下がっていた方が使いやすいと感じるので。
「身長の65%の長さ(身長 × 0.65)」
私の場合、147× 0.65=95.55cm。登りでは90〜95cm、下りでは95〜100cmが使いやすいので、目安の計算式ですが割と的を得ています。
重量に関しては、"どんなスタイルで使いたいか"を考慮するとよいかと。登山中は基本的にずっと使いたい、下りの補助メインで使いたい、念のため携行したい・・・など。
しっかり使いたいなら耐久性や使い勝手を優先、軽めのバランス補助や携行メインなら軽量性を優先、などスタイルに合わせて。
その他細かい仕様
大まかな選び方に加え、メーカーやモデルごとに仕様や各パーツの素材は細かく異なります。
◾︎ グリップの素材・形状
◾︎ ストラップの素材・調節機能
◾︎ バスケットの大きさ・形状
◾︎ シャフト連結素材(フォールディング式)
◾︎ 修理対応について
アンチショック機能
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
バネが内臓され、手が受ける衝撃を和らげる「アンチショック」という構造になっているモデルがあります。
コンクリートや岩のような硬い地面に対して特に効果的ではありますが、個人的には「そこまで重要か?」とも思います。
パーツが増えることで重量が増し、故障箇所が多くなるのも少し厄介かなと。
グリップの形状・素材
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
グリップ(握る部分)の形状は、しっかりした凹凸があるものからフラットなものまでバリエーション豊か。
男女兼用と女性用で分かれているモデルもあるので、自分の手にフィットするかの確認はとても重要。
素材は、吸汗性に優れた「EVA」が主流。暑い時期でも快適に使えます。「コルク」は手に馴染む素材ですが、現在はほとんど見かけなくなりました(まだある?)。吸汗性は「EVA」に劣ります。
ストラップの素材・調節機能
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ストラップは、丈夫なものから風の通しが良く軽量な素材までさまざま。

保水しにくい軽量な「モノフィラメント」
ストラップを活用する場合、肌にピタッと接触するので結構暑いです。雨で濡れると乾きづらかったり、汗と混ざって嫌な臭いを発したり。「モノフィラメント」のような素材は夏でも使いやすいです。
また、ストラップの長さは調節可能か、調節システムはスムーズか(片手でできるか)なども合わせて確認を。
バスケットの大きさ・形状・互換性
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トレッキングバスケットは、地面や岩の隙間などに深く入り込まないようにするためのパーツ。
雪山でも使う場合は、雪山用の「スノーバスケット」に交換できるかの確認を。
また、付属のバスケットよりも小さくて軽量なものに交換できるモデルもあります。
モンベルでは、上記の写真のような、バスケットの一部が欠けているデザインの「コンパクト トレッキングバスケット」が販売されています。
収納時のかさばりを抑え、軽量化されたものです。オプションパーツがある場合、付け替え可能なモデルかを確認するとよいです。
シャフトの連結素材
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

折りたたみ式は、多くの場合コード(紐)でシャフトが連結されています。
画像出典:Yahoo!ショッピング
コードの保護や、組み立てをスムーズにするために樹脂で覆っているものもあるので、使いやすいものを。
修理対応について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
衝撃を与えてしまいがちなトレッキングポールは、修理が非常に多いギアのひとつ。購入後すぐに折ってしまうことも珍しくありません。
そのため、修理のアフターサービスがあるメーカーを選ぶと安心です。メーカーによっては「正規店舗での購入品以外は修理不可」という場合もあるので、ネットでの購入などは要注意。
モンベル「U.L. フォールディングポール 100」を選んだ理由
"軽量コンパクト"に加え、「U.L. フォールディングポール100」を選んだ理由は主に3つ。
◾︎ シンプルな構造で故障が少ない
◾︎ ツエルトをギリギリ張れる(ワンポールテントは、100では長さが足りない)
調節不可だけど90cmから使える
「U.L. フォールディングポール」は、長さの調節はできませんが、グリップ(持ち手)部分が20cmあるので、持つ位置を変えることで長さを調節できます。
グリップの長さは自分の手のちょうど2個分くらいで、10cmほどの長さ調節が可能。最短で90cmから使えます。
私の場合、下りでも100cmあれば十分なので"全長100cm、最短90cmからOK"というサイズがぴったり。
同じ100cmでマウンテンキング「Trail Blaze」も検討しましたが、握る位置を変えられないので却下。
重量は125g(アルミ)でモンベルより軽量。グリップの感触も良かったですが、90cmから使いたい自分にとってはやはり長い・・・
シンプルな構造で故障が少ない
シンプルな構造のメリットは"故障が少ない"こと。砂が固着して動かない、パーツが壊れた、などの不具合が極端に少なくなります。
「U.L. フォールディングポール」で何かあるとしたら、紐が切れる、ストッパーのラチェットボタンが出てこない、とか。
しかし、いずれもダクトテープがあればその場凌ぎできるかな?程度だと思います。
\ 登山の「リペアキット」についてはこちら /
ツエルトをギリギリ張れる
ワンポールテントは長さが120〜125cm程度必要なので使えませんが、ツエルトなら100cmでも可能。105〜110cmくらいが理想ですが、チビなので天井が多少低くても問題ない。
ワンポールテントは軽量ですが、自分がトレッキングポールに求める長さとワンポールテントに必要な長さが一致しないので、今後も使うことはなさそう。
トレッキングポールを使う頻度の方が多いので、そちらを優先に考えました。エマージェンシーとしても、テントを軽量にするとしてもツエルトかなと。
*「大峰奥駈道」でマダニに咬まれ、テントの軽量化にツエルトを使う選択肢も自分の中でなくなりました
\「マダニ」と「軽量化のリスク」について /
「U.L. フォールディングポール100」概要

\「U.L. フォールディング」の長さは4種類 /
| サイズ・重量 | ◾︎ 100(90〜100):149g ◾︎ 105(95〜105):152g ◾︎ 113(103〜113):157g ◾︎ 120(110〜120):163g *カッコ内は使用可能な長さ *重量はポイントプロテクター10g含む |
| 収納サイズ | ◾︎ 100:32cm ◾︎ 105:34cm ◾︎ 113:36cm ◾︎ 120:39cm |
| 素材 | ◾︎ シャフト:アルミニウム合金 ◾︎ グリップ:EVA ◾︎ ストラップ:ナイロン |
| *2023.4時点の情報 |
モンベルはトレッキングポールを1本売りしているので、1本使いをしたい、片方紛失した、修理料金の方が高くなる、という場合も気軽に購入できることがメリット。

シャフトの連結は紐

上・中・下段の太さはすべて同じ。下段に合わせて中→上段とはめて連結させ、グリップ部分をグッと上に上げると、ストッパーのラチェットボタンが出てきてロックされます。
ロックを解除するときは、ラチェットボタンを押してシャフトをバラバラに。

グリップには溝があり、握ったときに滑りにくいデザイン。一番下には、折りたたんだときにまとめるマジックテープが付いています。

バスケットはコンパクトな半円形。収納時にかさばらない仕様。
*「U.L. フォールディングポール」は雪山用の「スノーバスケット」は付けられません。また、別売りの「コンパクト トレッキングバスケット」も取り付け不可

ストラップは長さ調節可能で、少しクッション性があります。特別、軽量仕様ではないですね。
3,000kmのロングトレイルでも大活躍!「U.L.フォールディングポール 100」使用レビュー
トレッキングポール購入の一番の目的は、ニュージーランドのロングトレイルで使うため。ロングトレイルでの使用感を交えながらご紹介します。
\「U.L. フォールディングポール」のここがいい!/
◾︎ 片手で2本持ちできる
◾︎ 軽くて取り回しが軽快
◾︎ 軽量だけど耐久性がよい
◾︎ メンテナンスが容易
凸凹がないフラットグリップが使いやすい

凹凸があるグリップだと握る部分が決まってしまいますが、フラットなグリップは"どこを持ってもいい"というラフな感じがよい(溝は滑り止め)。
私はちょっとした補助として使うことが多く、しっかり握っている時間が少ないので、握る部分が決まっていると逆に窮屈に感じてしまいます。
夏場、手汗をかいたら位置をズラしたり、自由度の高くて使いやすい。
片手で2本持ちできる

凹凸がなく、グリップが細いため、片手で2本まとめて持つことができます(手は小さいけど可能!)
ちょっとした岩場を通過するとき、片手を開けたいとき、平地で2本使いをしなくていいとき、2本使いに疲れたときなど、2本まとめて持てると便利。
ニュージーランドのロングトレイルでは、キャンプ場の3〜4km手前のスーパーに寄り、片手にストック2本、片手にエコバッグで歩いたこともしばしば。
軽くて取り回しが軽快

大峰奥駈道
149gと軽いので、一日中使っていても、疲れてきたときの急登でも、トレッキングポールを持っていることが苦になりません。
また、手の力がトレッキングポールの重さに負けないので、少しスピードハイク気味に歩くときも取り回しが軽快。
はじめの1本がこの軽さだと、これ以上のトレッキングポールが重くて使えなくなりそうです。
軽量だけど耐久性がよい

シャフトが細いので、「折れやすい」「頼りなさそう」という印象を受けますが、実際に使ってみると意外と丈夫でした。

ニュージーランド / 渡渉の干潮待ち

10日分の食料を詰め込んだ
「テ・アラロア」で、一番長い山の縦走は8日間でした。予備食を含めて10日分の食料を詰め込んだザックは18kg(水含む)。
アップダウンと渡渉三昧の山脈で、何度か体重をかけてしまい「やばい!」と思いましたが、少しも曲がることなく3,000kmを踏破。
同じ細さでカーボンだったら折れていたかもしれません。細いながら、アルミの粘り強さを実感しました。
購入してから故障のトラブルは一度もなく、シンプルなつくりにも満足しています。
メンテナンスが容易
使用後は、全体的に汚れを拭き取り乾燥。砂や塵が隙間に入り込むようなパーツはないし、コードで連結されているのでシャフトを失くすこともない。
「ツイストロック」や「レバーロック」のポールよりも、メンテナンスは容易だと感じます。
修理の際は自分でシャフト交換ができないため、バラせる伸縮式に比べると時間がかかりますが(バラせるものは"パーツ取り寄せ"で対応してもらえる)それは仕方ない。
【デメリット】「U.L. フォールディングポール」の気になる点
*調節ができないデメリットはグリップの長さで補っているため、今回はデメリットから省いています
マジックテープがちょっと面倒

グリップには、折りたたんだ際にまとめるマジックテープが付いていますが、これがちょっと面倒だと感じています。
失くさない、いちいち取り出さなくていい、というメリットはありますが、2本使いの場合1本ずつまとめるのが面倒くさい。

マジックテープは取り外せるので、別のバンドで2本まとめるか、片方のマジックテープで2本一緒にまとめる方がらくかと。

片方のマジックテープを取り外し、2本まとめた状態。マジックテープを失くさないメリットは活かしたいので、この方法に落ち着きました。

しかし、使い始めてから1年以上経つとマジックテープの粘着が弱くなり、2本まとめるのが少し困難(緩い)になってきました。
取り外したもう1本がありますが、それもダメになったら何かバンド的なものを考えます。
ストラップ素材が少し暑い

ストラップの素材は多少クッション性があり、特別軽量な訳ではありません。
春でも少し暑さを感じ、夏は普通に暑い。夏山は縦走やテント泊が多いので、個人的には、モノフィラメントなど薄めの方がありがたい。
はじめはストラップを使用していましたが、途中から煩わしくなり取ってしまいました。
必要になったときまた使えるように、ストラップ本体を切らない取り方をしたら大失敗。結果的に修理になりました。
ストラップを外すことをお考えの方は、下記記事をご覧ください。ストラップを切ることによる修理時のデメリットも記載しています。
まとめ
海外ロングトレイルの装備として、また、身体への負担を減らすために購入したモンベル「U.L. フォールディングポール100」をご紹介しました。
「長さ調節ができない = デメリット」となりがちですが、グリップが長いことで、個人的にはデメリットにならず。むしろ、使いやすい。
シンプルな軽量ポールであるがゆえ、使い方が限られる場合もありますが、過酷な登山やロングトレイルで実際に使用し、想像以上に丈夫で、UL(ウルトラライト)ながら使える幅が広いことを実感。
◾︎ 身体への負担を少し減らしたい
◾︎ ちょっとしたバランス補助がほしい
軽量コンパクトなトレッキングポールをお探しの方は、ぜひご検討ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
\ 記事がお役に立ちましたら /
よろしければ、応援よろしくお願いいたします。
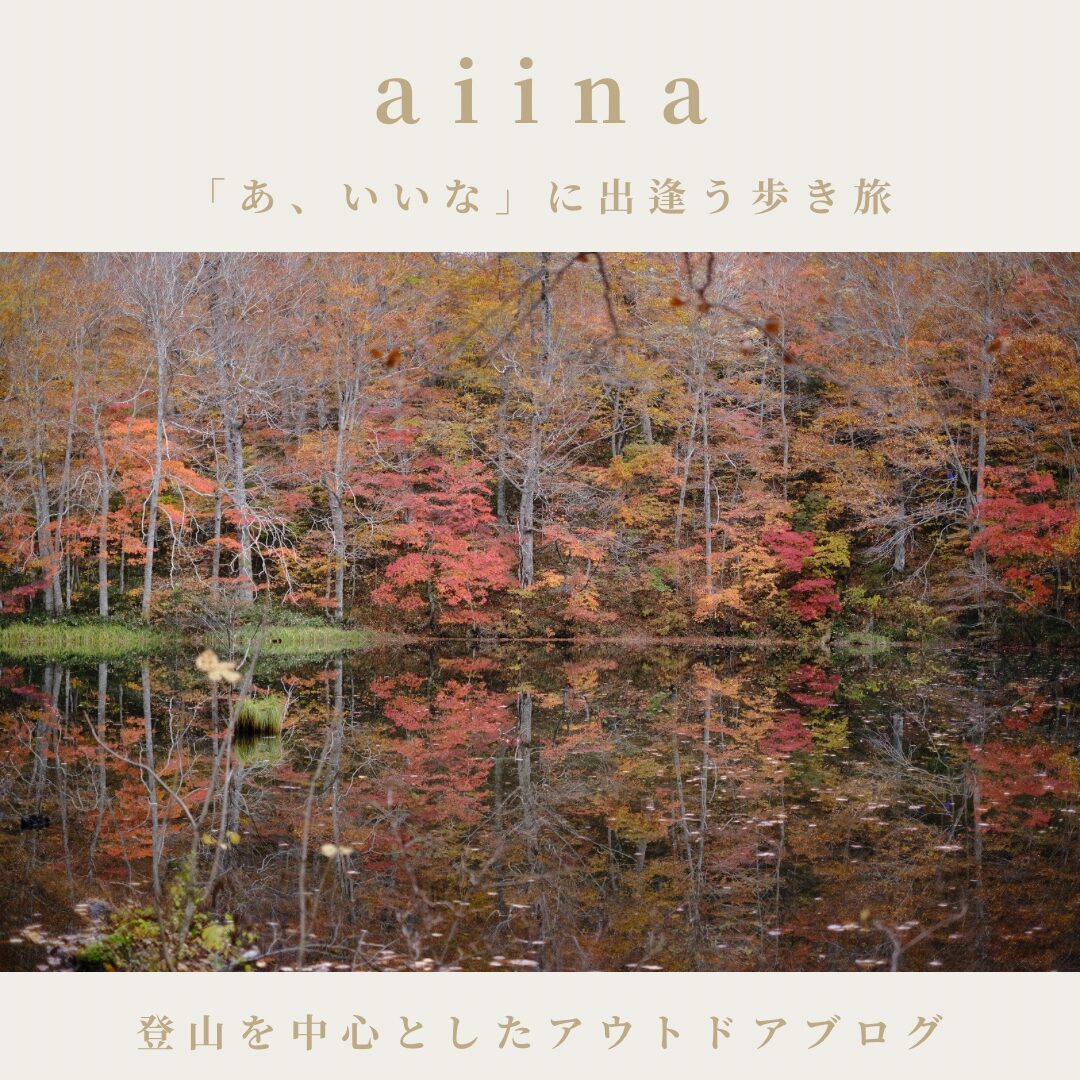










コメント